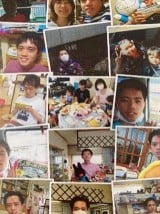わかば会研修センターではわかば会利用者の成長、主体的で自立した職員の育成、多様な人たちが支え合いともに成長できる地域の3つを目指して、交流や体験を通した学びの場づくりをしていきます。
□ 研修の申込・問い合わせ先
TEL 0897‐66‐8800
e-mail wakaba01@iaa.itkeeper.ne.jp
(多目的利用スペース リーフ内)
研修予定
ほんしつとエピソード(2024.4)
話し手:井川卓(くすのき園 園長)
テーマ:矛盾
日 時:4月26日(金曜日)18時~19時30分
会 場:新居浜市総合福祉センター2階第1研修室
ほんしつとエピソード(2024.5)
話し手:青木悠氏
社会福祉法人今人倶楽部 理事長
プログレス株式会社「四つ葉」取締役
株式会社ダンク「だんだん」取締役
四国中央医療福祉総合学院 非常勤講師
テーマ:妄想から創造へ
日 時:5月24日(金曜日)18時~19時30分
会 場:新居浜市総合福祉センター2階第1研修室
ほんしつエピソード(2024.6)
話し手:尾鼻晃(くすのき園 支援主任)
テーマ:生活支援員として学んだ15年プラスアルファ
日 時:6月28日(金曜日)18時~19時30分
会 場:新居浜市総合福祉センター 2階第1研修室